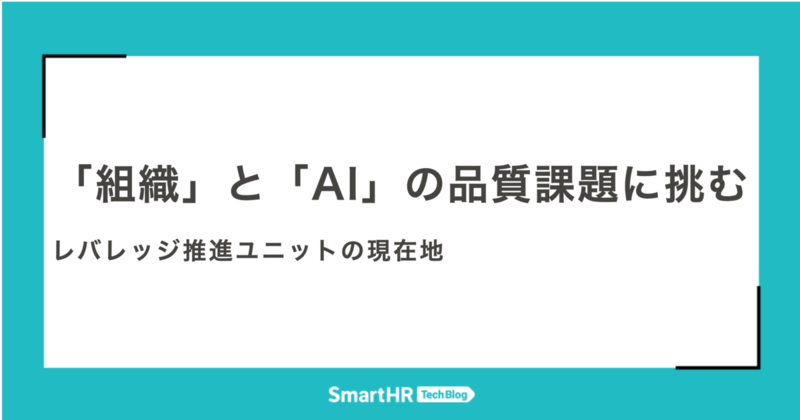
前回の記事(レバレッジ推進ユニットが目指す「全社を巻き込んだ品質課題の解決」)では、私たち品質保証部直下のoverallユニットが「レバレッジ推進ユニット」として新たにスタートした経緯と、SmartHR全体の品質向上に対して組織横断的にレバレッジをかける活動に注力していくお話をさせていただきました。
今回は、ユニット発足からこれまでの具体的な取り組みの一部と、その中で得られた学びや今後の方向性についてご紹介します。特に力をいれている「部門横断での品質向上へのアプローチ」および「AI活用プロダクトの品質保証方法の選定と検証」という二つの取り組みを中心にお伝えします。
部門横断での品質向上へのアプローチ
前回の記事でも触れましたが、全社へのレバレッジ施策の第一歩として、まずはビジネスサイドの方々へのヒアリングを行ないました。これは、お客様の利用実態に近い視点からの品質課題や、ビジネス上の期待値を深く把握し、より効果的な施策検討に繋げていきたい、という目的からです。プロダクトマーケティングマネージャーやカスタマーサクセスをはじめとする関係部署の方々に協力いただき、部署を横断して品質に関する現状の認識や課題感についてお伺いしました。
ヒアリングから見えてきたこと
ヒアリングを通して、様々な立場からの貴重なご意見をいただきました。今後のプロダクト品質向上に向けて、期待や課題感は以下の通りです。
- より快適な利用体験の追求
- 複数のプロダクトをまたいで利用する際のシームレスさの向上や、学習コストが低く直感的で迷わない操作感など、お客様がストレスなく、心地よくサービスを利用できる体験を目指すことへの強い期待
- プロダクト全体の継続的な品質向上
- 新機能リリース時はもちろんのこと、既存機能も含めたプロダクト全体の安定性や信頼性を継続的に高め、お客様が常に安心して利用できる状態を維持することの重要性
- 様々な利用環境への対応:
- お客様が利用される多様な環境、また、従業員数など利用規模が拡大した場合においても、一貫して期待されるパフォーマンスを発揮し、快適な動作速度を維持・向上させていくことへの関心。
同時に、現状のプロダクトに関する多くのポジティブなフィードバックもいただくことができ、大変励みとなりました。一方で、以下のような組織横断的な取り組みを進める上での課題や気づきも得られました。
- 品質に対する理解度の差
- 部門や立場によって、「品質」という言葉で想起するものや重視するポイント(例:機能の正確性、使いやすさ、パフォーマンス、セキュリティ、プロダクト間のスムーズな連携・一貫性など)に違いがある
- 品質保証活動の認知とコミュニケーションの課題
- 品質保証活動やその成果を十分に伝えきれていない現状があり、そのため、品質保証領域の解像度の低さや、普段直接関わらない職種へその意義が十分に伝わっていないことに課題があると感じた。今後はより分かりやすく積極的な発信が必要
- 全社横断の難しさ
- 関係部署それぞれのミッションや優先度、業務サイクルの違いなどがある中で、共通の目標を設定し、協力体制を築き、具体的なアクションに繋げるプロセスに、特有の難しさがあることを認識した。関係者間の丁寧な合意形成が求められると感じた
課題解決に向けたアプローチと今後の方向性
これらのヒアリング結果を分析し、見えてきた課題に対する改善仮説を立て、具体的なアクションプランを計画してみました。いくつかのアクションを試みる中で、全社的な連携をより円滑に進めるためのコツ(早期の関係者巻き込み、目的・ゴールの明確化、関係性の構築など)や、当初の仮説に固執しすぎず、状況に合わせて柔軟に進め方を変えていく大切さなど、学びも多かったです。また、短いサイクルで仮説検証を回すことの価値を改めて感じています。
この学びを踏まえ、現在は当初のアプローチを少し見直しながら、より効果的で継続しやすい協力体制を築くための準備を進めています。具体的には、関係のある部署との連携を引き続き深めつつ、これまであまり接点が少なかった部署とも積極的に対話の機会を設け、お互いに理解を深めながら、協力の土壌作りを進めていきたいと考えています。
これらの取り組みは、すぐに大きな成果が出るものではないと思いますが、中長期的な視点で粘り強く推進していくことが大事だと考えています。
AI活用プロダクトの品質保証方法の選定と検証
SmartHRはAI技術を重要な要素と捉え、既存プロダクトの強化や新規開発においてAI活用を積極的に進めており、結果としてAI関連のプロダクト開発が増加している状況です。
そのため、AI活用プロダクトの品質保証をどう行なうかは、公平性や安全性、透明性などに十分配慮した責任あるAI活用を進めるうえで優先すべき課題です。これはお客様からの信頼にも繋がる大切な視点だと考えています。
当ユニットでは、品質保証部の他のユニットや各開発チームが、迷わず、かつ効果的にAI活用プロダクトの品質保証に取り組めるよう、その基盤となる考え方や具体的な手法の調査・整理を進めています。
もちろん、品質保証部内では「品質保証活動やテストにAIを活用する」取り組みも進んでいますが、そちらについては、別の機会にご紹介したいと思います。
現状理解と知見収集の取り組み
AI活用プロダクトの品質保証は変化の激しい分野であり、当ユニットも最新動向を学びながら、SmartHRに適した方法を確立しようとしています。
当ユニットではまず、AIに関する品質保証について、世の中の動向や社内の現状を把握することから始めました。具体的な活動としては以下のようなものがあります。
- 基礎知識のインプット
- 「AIプロダクト品質保証ガイドライン (QA4AI Guidelines)」や産業技術総合研究所の「機械学習品質マネジメントガイドライン」といった国内の主要な公開資料を参照し、AI品質保証に取り組む上での基本的な考え方やフレームワークについて調査する
- 社内ヒアリング
- AI活用プロダクトを担当するプロダクトマネージャーやプロダクトエンジニアに対して、ヒアリングを実施。プロダクトの目的やAIの活用方法、現状の開発プロセスや品質保証への取り組み状況、利用している技術要素、そして私たちQAエンジニアに期待する役割など、現場の実情や具体的な課題感について把握する
- 既存プロダクト資料の参照
- 社内の既存AIプロダクト開発チームによるテスト、性能評価、セキュリティテスト等のアウトプット資料を参照し、AIプロダクトならではの評価方法や手法について理解する
活動で得られた知見をもとに、業界動向も参考にしつつ、SmartHRのAI技術開発を推進するHead of AIやプロダクトエンジニアと協力し、SmartHRならではのAI活用プロダクトに対する品質保証のアプローチの具体化を進めています。
今後に向けた計画
現在進行中の調査・ヒアリングに加え、今後は以下の活動を行ない、取り組みをさらに具体化していく予定です。さらに、社外の有識者や他社の事例から知見や示唆を得るために、積極的に情報交換を行ない、取り組みをより良いものにできれば、と考えています。
- ドキュメント作成
- AI活用プロダクトの品質保証を行なう際に、開発チームや品質保証部の他のユニットが共通の理解を持ち、具体的なアクションの拠り所とできるような参考資料やガイドラインを作成。これにより、各チームが効率的かつ効果的に品質保証活動を進められる状態を推進する
- 社内プロダクトでの技術検証
- SmartHRのAI活用プロダクトに対して、調査・整理した品質保証のアプローチを適用する技術検証、方法論の検証を実施。実プロダクトでの適用を通して有効な手法やツール、実運用上の課題点などを具体的に明らかにし、その結果をガイドライン等にフィードバックする
これらの活動を通して、SmartHRにおけるAI活用プロダクトの品質保証に関する基本的な考え方や具体的な進め方を整理・体系化し、品質保証部の他のユニットや各開発チームに展開することで、各チームにおけるAI活用プロダクト開発を加速させ、全社的なレバレッジに繋げていきたいと考えています。
おわりに
本記事では、レバレッジ推進ユニットの主な取り組みと今後の計画の一部をご紹介しました。
レバレッジ推進ユニットは、ビジネス部門を含むあらゆる部署で品質保証に対する視座を高め、それぞれの職種の多様なバックグラウンドを活かした視点で、多角的に品質課題を発見・改善を推進できる状態を目指しています。
規模拡大、急成長を続けるスケールアップ企業である現在のSmartHRにおいて、横断的な品質保証に深く関与できることは、貴重な機会です。AI品質保証のような新しい領域も含め、変化し続ける組織の中で、部門間の連携を促進しながら品質施策を形にしていく経験そのものに、大きな価値とやりがいを見出しています。
私たちの取り組みは広範かつ新しい領域にわたっており、推進にはさらなる人員や専門知識が必要です。品質保証の領域にとどまらない多様なスキルセットも求められるため、これらの挑戦に一緒に取り組んでくれる仲間を積極的に募集しています!
We are Hiring!
この記事を通して、レバレッジ推進ユニットが取り組む組織横断での品質向上やAI活用プロダクトの品質保証といった取り組み、そしてSmartHRのレバレッジ推進ユニットが目指す方向性や価値について、少しでも興味を持っていただけたでしょうか。
もし「この取り組みをもっと推進してみたい!」「もう少し詳しく話を聞いてみたい!」と感じていただけたなら、カジュアル面談をぜひご検討ください!私たちと一緒に、全社的な視点と横断的な活動を通じて、SmartHRの品質レベルの成長を支えていきましょう!