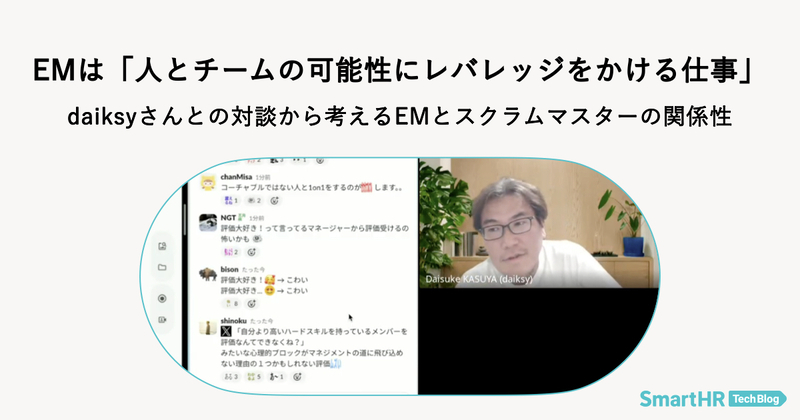
こんにちは、SmartHRでアジャイルコーチをしている@wassanです。
2025年6月12日と19日、SmartHRの社内勉強会「アジャイルやっていきの集い」特別会として、株式会社はてなのエンジニアリングマネージャー(EM)であり、スクラムやScrum@Scaleに関する著書を持つ@daiksyさんをお招きし、2週にわたって対談を行いました。
今回、daiksyさんに対談を依頼した背景には、いくつかの理由がありました。SmartHRでは、現在、Scrum@Scaleの組織的な導入を進めており、EMとスクラムマスターの役割を整理し、よりよい形で統合したいと考えていました。そのため、Scrum@Scaleの組織導入の経験があり、はてなで現在EMの体系的な育成支援の仕組みづくりに取り組まれているdaiksyさんの知見を、ぜひ伺いたいと思いました。また、EMという役割のやりがいや魅力についても、SmartHRメンバーに広く知ってもらい、今後のキャリアパスの参考にしてほしいという思いもありました。
EMの役割、スクラムマスターとの関係性、キャリアとしてのEMの面白さ、そしてAI時代のEMの未来像について深く掘り下げたこの対談。SmartHRメンバーにとっても多くの気づきがあった内容を、ブログ記事としてお届けします。
「EMとスクラムマスターは別物」という前提を疑ってみる
EMとスクラムマスターを両方経験したdaiksyさんは、「両者は似たスキルセットを持つ職能」と語ります。
「チームの観察、メンタリング、ファシリテーションなどはどちらも共通する。だけど、評価者がスクラムマスターを兼ねることの難しさは実際にある」
はてなでは、EM候補がまずスクラムマスター的な役割を経験することが多く、「スクラムマスターは学ぶべきスキルが明快で、EMの入り口として非常に学びやすい」と考えられているそうです。
一方で、EMは評価や目標設定といった「権限」も持つため、チームの心理的安全性への配慮が不可欠です。daiksyさんは、EMとスクラムマスターを兼任する場合には、発言時に「どの立場から話しているか」を明言する、またはスクラムマスターの役割をメンバーに委譲するなどの工夫をしていたそうです。
スクラムマスターの成長と、EMへのつながり
Zuzana Sochovaさんの「Scrum Master Way(スクラムマスターの道)」では、スクラムマスターの成長段階が次の3つに分類されています。
チームを見る
関係性を見る
組織や社会を含めたシステム全体を見る
レベルが上がるごとに影響範囲が拡大し、レベル3に至るとEMと重なる部分が多くなります。SmartHRでも、スクラムマスターからEMへとキャリアチェンジする人が多く、EMとスクラムマスターは「違う道」ではなく、同じ道の途中で交差するような関係として理解されています。
EMに必要なスキルは「4つのマネジメント領域」
はてなでは、EMの役割を以下の4領域で定義しています。
ピープルマネジメント(メンバーの成長支援や評価)
プロダクトマネジメント(プロダクトオーナーとの連携)
プロジェクトマネジメント(プロダクト開発の進捗管理、障害物除去)
テクノロジーマネジメント(技術的支援)
daiksyさんは、「一人のEMがこの4つすべてに秀でる必要はない。むしろ自分の強みを活かし、EM同士がチームとして補完し合うことが重要」と語ります。
この考え方はSmartHRでも共感が多く、EMを「個人のスーパースター」ではなく「役割の連携体」として捉える視点は、今後ますます重要になるでしょう。
「EMになりたくなかった」から始まったキャリア
「最初は、まだエンジニアとして手を動かしたい気持ちが強くて、マネージャーの話は何度も断っていました」と語るdaiksyさん。
そんなdaiksyさんに転機が訪れたのは、はてなに入社してからのこと。まわりには自分よりも優秀なエンジニアが多く、「では自分はどう貢献できるか?」と考えたとき、自然と自身が持つ「アジャイルやスクラムの知識」に目を向けるようになったそうです。
アジャイルやスクラムをチームで活かしていくには、スクラムマスターやアジャイルコーチとして、対話を促したり、気づきを引き出したり、時にはチームの背中をそっと押すような関わりが求められます。こうした関わりの中で、人が変わっていく様子、チームが成長していくプロセスに立ち会えることに面白さを感じたことが、EMというキャリアを選ぶ大きなきっかけになったそうです。
「レバレッジをかける」というEMのやりがい
daiksyさんは、次のような「レバレッジが効いた瞬間」に、EMとしてのやりがいを感じるとのことです。
1on1でのコーチングを通じて、メンバーが大きく成長する瞬間
メンバー同士が自然に助け合い、主体的に動くようになったと感じる瞬間
また、マネジメントとは「生まれながらの素養」ではなく「トレーニングによって身につけるスキル」であるという認識も共有されました。プログラミングの技術と同じように、学んで、実践して、成長する。それがEMという職能なのです。
AI活用の促進におけるEMの役割
AI活用が進む中、はてなではまだPoC(Proof of Concept、概念実証)や検証段階にありますが、EMの役割はAI活用の「推進者」よりも「障害を取り除く支援者」に近いと言います。
AI活用のためのツールの予算や法務との調整
AI実装に向けたセキュリティ・ガバナンス対応
これらはスクラムマスターが担う「障害除去」の役割とも重なります。メンバーがスムーズに試行錯誤できる環境を整えることが、今のEMに求められる支援なのです。
EMのキャリアラダーと感情知性(EQ)の重要性
はてなでは、EMの4つのマネジメント領域に応じたキャリアラダーの整備が進められています。これにより、各EMが自分の現在地と成長目標を可視化できるようになります。
対談の後半、SmartHRのEMであるyuzuruさんから「キャリアラダーにEQなどの非認知スキルも含まれているのか?」という質問があり、daiksyさんが自身の考えを語ってくれました。
「プロジェクト管理や技術支援などのAIが得意な分野は今後EMの役割から離れていく。だからこそ、他者への共感や意欲を引き出すコーチングといったEQが、EMにとってより重要になってくる」
信頼関係の構築、対話、対立管理、ビジョンの提示など、AIには担えない「人間的な仕事」こそ、今後のEMの存在意義になる。だからこそ、キャリアラダー設計にEQのような非認知能力を組み込むことが不可欠になるというメッセージは、非常に印象的でした。
評価が苦手でも、EMになれる?
対談の終盤では、「人を評価するのが苦手」「自分より優秀な人をどう評価すればよいか」といった悩みが話題になり、daiksyさん自身の考えも共有してくれました。
「正直、今でも『人を評価するのは苦手』。でも、EMは『自分を棚に上げてでも役割を果たす』スキルが求められる。必ずしも自分が相手より優れていないといけないわけではない」
評価の際は主観ではなくファクトベースで接する姿勢が重要。自分よりもスキルの高いメンバーに対してでも、継続的な1on1や目標設定・振り返りを通じて、相手の成長支援に貢献できるという実践的な示唆が得られました。
まとめ
今回のdaiksyさんとの対談を通じて、EMとは、多様な背景と強みを持つ人たちが、チームと組織にレバレッジをかけていく仕事であると再認識できました。
また、スクラムマスターとEMは分断された役割ではなく、相互に重なり合いながら、進化していくパートナーなのだと改めて実感しました。
そして、AIの時代が進む今だからこそ、人間らしさを活かすマネジメントが、EMにとってより大切になります。
この記事が、EMというキャリアに興味がある方、あるいは今まさに悩んでいる方にとって、小さなヒントになれば嬉しいです。
最後に、今回の対談において、豊富な知見やご経験を惜しみなく共有してくださったdaiksyさんに、心より感謝申し上げます。
daiksyさんのお話から多くの学びと気づきを得ることができました。本当にありがとうございました。
We Are Hiring!
SmartHR では一緒に SmartHR を作りあげていく仲間を募集中です!
アジャイルやスクラムをベースとした、人とチームの可能性を広げるマネジメントに興味がある方のご応募をお待ちしています。
少しでも興味を持っていただけたら、カジュアル面談でざっくばらんにお話ししましょう!