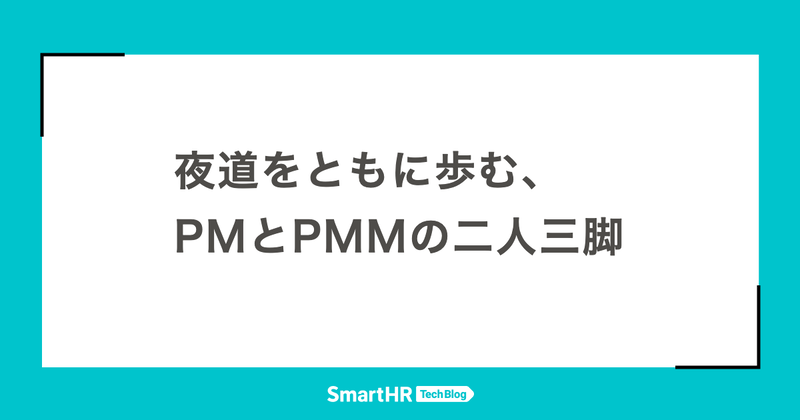
こんにちは。SmartHR プロダクトマネージャーの山根(@sayama)です。
「SmartHRのプロダクトマネージャー(以下、PM)って、他職種との分業が進みすぎていて、自分の裁量で動ける範囲が狭いんじゃない?」こんな質問をよく受けます。確かに一見すると、専門職種を多く抱えるSmartHRでは、PMの仕事範囲が限定的に見えるかもしれません。
特にプロダクトマーケティングマネージャー(以下、PMM)については、「ディスカバリーフェーズはPMM任せなの?」という誤解を受けることがあります。しかし、実際はその逆です。専門性を持った仲間と協業することで、PMはより本質的な価値創造に集中できる環境があるんです。そこで今日は、私とPMMとの協業エピソードを紹介したいと思います。
暗中模索な領域で感じた不安と心残り
協業事例紹介の前に、少しだけ自分語りをさせてください。
いま私は労務プロダクトの主に従業員データベースに関わるプロダクトのPMをしています。入社して1年半が経過しますが、従業員の情報を適切に蓄積・活用できるプロダクトにできるように日々格闘中です。
前職では東南アジア向けAI SaaSのプロダクトマネジメントを担当し、企画〜開発〜GTM〜セールス戦略まで中央集権的な立場で統括していました。それはそれでやりがいがあり、グローバルの仲間といっしょにチャレンジする環境は興奮するものでした。
一方で、自分自身も暗中模索な領域で意思決定をするときに特に事業的な観点でフィードバックを得られる環境になかったことに不安を感じていたのもまた事実でした。たとえば、インドネシア市場への営業戦略として複数の再販パートナーを獲得することを事業部内で提案したときに、オープンな問いかけをしても現地商習慣を意識したような建設的な代案やフィードバックを吸い上げられないまま再販パートナー探しを実行に移したことがあります。
幸運にも良い再販パートナーを見つけることはできましたが、今思い返すと自分の専門外の領域における提案や意思決定に対してフィードバックを得られないことが不安の種だったと感じます。もっとうまくやれなかったのか、いまでも振り返ることがありますが、答えは見つかりません。
分業ではなく協業
以下で紹介するのは、SmartHRの「部署コードで従業員を登録できるようにする」という機能を開発したときの話です。
課題背景
これまでSmartHRでは部署名のみでしか従業員登録ができませんでした。しかし多くの企業、特に大企業では、社内の基幹システムで部署コードを管理していることが一般的です。そのため、SmartHRに従業員情報を登録する際には、取り込みファイルの加工作業が必要となり、担当者の大きな負担となっていました。
具体的な役割分担と協業
そこで、以下のように役割分担しながら、開発からデリバリーまでを進めることにしました。
- PMがやったこと
- 課題の整理と優先順位付け
- ユーザーストーリーの作成
- 実際のユーザーへのヒアリング
- プロダクトロードマップへの組み込み
- PMMがやったこと
- ビジネスサイドへの展開と期待値のすり合わせ
- 実際に課題を解決できているかを計測するための顧客アンケートの実施
- 機能実装後のフォローアップと活用促進
一見すると分業しているように見えますが、実際にはヒアリングには二人で参加し、ユーザーストーリーの作成時にもディスカッションを重ねました。
PMとPMMの視点の違い
振り返ると、PMとPMMはそれぞれの観点を持って、多角的に議論できていた気がします。
- PMの観点
- 外部システムとSmartHRの併用において、業務上の負荷を下げる価値を提供することが目的。
- 特に企業の担当者が定期的に行う従業員情報更新作業の効率化を重視していました。
- PMMの観点
- 部署コード取り込みができないために、これまでSmartHRで組織管理自体を行っていなかった企業に対して新たな価値を提供できる可能性に着目。
- 組織管理ができるようになることで、タレントマネジメントなどSmartHRの他のプロダクト活用にも広げられるという、より広い視点での事業拡大の可能性を見ていました。
つまり、私が機能面から提案し、PMMがビジネス視点からフィードバックする——この協業プロセスが、より価値の高い機能設計につながりました。
成果と気づき
この機能は、大企業を中心に非常に好評でした。まだリリースして間もないためSmartHRの他の機能も活用し始めることに寄与できているかの検証はこれからですが、PMとしての私の視点だけでは見えていなかった事業拡大の可能性を、PMM視点が補完してくれたおかげで優先度高く取り組めた一例です。
PMMは夜道の懐中電灯
SmartHRにおけるPMとPMMの関係は、明確な境界線で区切られたものではありません。むしろ、役割がオーバーラップする「パートナー」という表現が最も近いでしょう。お互いの強みを活かしながら、足りない部分を補い合う関係です。
前述の機能開発よりももっと抽象度が高く、大きな課題に対するディスカバリーフェーズでも、PMとPMMは歩調を合わせてともに探索をしていきました。 機能開発のときと違うのは、最初の仮説立ての段階からいっしょに悩み、競合調査やヒアリングなどを通して土台となる仮説の検討をしてきたことです。PMMには事業インパクトの数値(金額)への落とし込みで頼ったり、プロダクトとしてのありたい姿は私が率先してビッグピクチャーを描いてPMMからのフィードバックをもらうように動くなど、要所では役割分担しつつもプロダクトや事業の目指す道のりをともに形にしていきました。
自分の中で仮説が具体化されていない状態からPMMが隣にいてくれるというのは、夜道を照らす懐中電灯を手に入れたような感覚で、不確実性に立ち向かう上で非常に心強い存在です。機能開発のときはPMMがいてくれるから確実に価値をデリバリーできるという安心感がありますが、抽象度が高いディスカバリーではPMMのおかげで一歩先に進めるという、より初期段階でのありがたみを感じていました。
目指すところは同じだから自信を持って歩める
協業の中で特に価値を感じるのは、考え方がシンクロした瞬間です。例えば、私が機能面から「この方向性が良さそうだ」と考えていたとき、PMMが全く別の角度(マルチプロダクトの観点、競合分析やマーケットトレンド)から同じ結論に至ることがあります。そんなとき、「異なる視点から同じ結論に達した」という事実が、意思決定に大きな自信をもたらしてくれます。また、行き詰まったときに、異なる視点からの問いかけが突破口になることも少なくありません。
PMとPMMの境界があいまいだということは、決してネガティブなことではありません。むしろ、お互いの専門性を活かしながら、共通のゴールに向かって進む仲間です。それぞれの強みを活かした協業により、より良いプロダクト、より大きな事業インパクトを生み出すことができると思います。
おわりに
SmartHRには、バリューの上位概念として「早く・遠くに・共に行く」という言葉があります。SmartHRのPMはまさに、他の専門職種がいるからこそ、本質的な価値創造に集中できる環境があります。特にPMMとの協業は、単なる役割分担ではなく、二人三脚で進む創造的なパートナーシップです。
もし「PMとして自分の裁量で1から10まで何でもやりたい」という方には少し物足りないかもしれません。しかし、「専門性を持った仲間と協力して、より大きな価値を生み出したい」という方には、理想的な環境だと思います。精神的な支えとなる仲間といっしょに、ひとりじゃないと思える環境で働ける幸せを日々噛み締めています。
【宣伝】SmartHRはプロダクトマネージャーを積極採用中です!
SmartHRのプロダクトマネージャー(PM)は、プロダクトマーケティングマネージャー(PMM)以外にも、さまざまな専門家の力を借りて、価値を生むことに集中できる環境です。ご応募お待ちしております!